太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
小川新 新論
小川新の瘀血(おけつ)論・腹証論・漢方東洋医学論/信仰と医療=無門居士東庵新の「言の葉」「書き付け」など備忘録・拾遺集=
ココログからのお知らせ
携帯URL
小川医院[漢方診療・針灸・ビワ葉温灸]
2007年6月
西丸和義“See And Do”と吉益東洞の“先物実試”
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
第1回瘀血総合科学研究会/昭和55年 (1980年) 2月22日 広島県医師会館にて
瘀血総合科学研究会の発足を祝して(祝辞)
西丸和義(にしまるやすよし)(日本脈管学会名誉会長)
"See And Do" と吉益東洞の "先物実試"
小川新(座長)
それでは、西丸先生がおいでになっていらっしゃいますから、ごあいさつをいただきたいと思います。先生は、お年は言わないということになっておりますが、日本の脈管学の近代の基礎を築かれた方でいらっしゃいます。若いときのケンブリッジ大学での研究の話、日本へ帰られてからの吉益東洞の“先物実試”の話をよく聞かされておりまして、我々はいつも敬意を表しているのですが、本日は、先生に何かご感想をいただければと思っております。
西丸和義
いまご紹介を受けました西丸と申します。実は私の名前は“和義”と書きます。それで、皆“ワギ、ワギ”と言うのですが、実は私の名前は“ヤスヨシ”というのです。このような研究などしないで商売をしたら、さぞかし成功する名前だと思うのです。安くてよいものを売れば、必ず成功しますから。
実はきのうお電話がありまして、第一回の瘀血学会をやるので、とにかく出てこい。出てこなければ、自動車を向けるからというわけで、引っ張り出されてきたわけです。いま座っておりますと、小川君が盛んに私の広告をするので、これでは参議院にでも立候補せいというのではなかろうかと思いながら、聞いておりましたが・・・。
第一、「おけつ」ということはよく分からないのです。それで私は、早速いただいたこのテキストを読みますと、杉原(芳夫)さんという方の定義が書いてあります。局所的な血滞症状と全身的な汚血症状からなる病的症候群だ。こういうことを書いてあるのです。ははあ、それでは多少循環をやる私にも関係があるのかなと思っておりました。[杉原芳夫:医師,病理学, 広島大学大学院環境科学研究科教授]
もうひとつのことを見ましたら、有地(滋)さんの名があったのです。何年か前に、漢方医学では組織間のことをやらなければならないのだということで私のところへおいでになりまして、私に、元気でおれというので、漢方のお茶を一箱、大きな箱でいただいたのです。まだ全部は飲みませんが。[有地滋:医師,近畿大学東洋医学研究所教授]
ああ、そうかなと思っておりましたら、ここに関西医科大学の先生で伊原(信夫)さんが、「骨盤うっ血と膠原病」ということを「漢方」という本に書いておられるのを見まして、ははあ、これはやはり有地さんがおっしゃったように、組織間が非常に関係があるのだろう、こういうことを考えたわけでございます。 [伊原信夫:医師,関西医科大学病理学教室助教授] 広島大学を定年になりますときに、ひとついままでやってきた体液循環、ハーベーの血液循環に代わって、体液循環を基本にした脈管学会というものを始めようというので、日本脈管学会が始まったわけです。
そのときは、170人が集まるのに大変だったのでした。初めのうちは演題がないのです。第3回まではだれも講演しないのです。仕方がないから、君、やれというので、その場をつくろったわけです。私などは20回のうちで13回特別講演をさせられるような状態で、やっと持ちこたえられてまいりました。
これがそろそろ脈管学というものが盛んになりまして、今日では会員が五千人近くなり、この前第20回がありましたが.演題も500題以上が出るようになりました。そして、初めの頃の助手の人、大学を出たばかりの人、今日も若い人がおいでになるかと思いますが、そういう方がこの二十年で研究に精進され、その人達の中からその後教授になられたり、方々の研究所の主任になられたりして、そして研究がまとまって、33題の特別講演ができるような状態になりました。
きよう、瘀血総合科学研究会はこれが第一回でございますから、いまお話を聞いておりますと非常に盛んで、討論も盛んですから、これは二十回をまたないで、十回ぐらいで大変な学会になるのではなかろうかと、心からのお祝いを申し上げる次第であります。
"See And Do"
なぜ脈管学会が盛んになったかと申しますと、これはそれに関連した疾患が多いからだろうと思います。脳卒中や心筋梗塞、動脈硬化で死ぬものが多いので、多くの人が注意をし、勉強するようになったりではありますまいか。
ところが、今日どうも脈管学会でも、組織間とリンパ管の研究が非常に手薄なのです。これはなぜかと申しますと、病気が発見されていないのです。組織間にいたっては、ここに書いてある膠原病がアメリカのニューヨークの人が初めて言い始めまして、やっと膠原病というものが脚光を浴びてきました。考えてみますと、この組織間というものは、クロード・ベルナールが言ったように、生命の根本になるところです。彼は、人間の生命というものは組織液、いわゆる細胞外液がコンスタントに保たれるかどうかが、生命の根本で、一番大事なところなのだと言ったのでした。
リンパ管というのは、今日はっきり分かっておりますことの1つに、リンパ液を流しっぱなしにすれば、死ぬわけです。また血管とリンパ管の間は神経によって絶えずコントロールされております。
私はシンシナティー大学で五十年前に、コロイドの大家のフィッシャー教授につきましたが、組織の浮腫、edema という仕事が彼の一生の仕事なのです。ところが、幾ら血液の中に水を入れましても、絶対に組織には水はたまらないで、皆毛細リンパ管の中に入ってまいります。言いかえれば、リンパ管は血液中の水と血圧、あるいはいろいろな老廃物、そういうもののコントロールをしているところということはよく分かっているわけです。今日、リンパ球が非常に大きな仕事をしていることもだんだん分かってまいりました。しかし、どうも研究が盛んにならない。それは病気が発見されないからではありますまいか。
先年、中南米に講演に行きましたが、あそこはリンパ管の研究が非常に盛んなのです。四年前に広島でリンパ管の国際シンポジウムをやりましたが、中南米の人が一番熱心で、しかもいい仕事をしておりました。これはなぜかと申しますと、あそこにはリンパ管に関係した風土病があるのです。ですから、世界で一番初めにリンパの学会ができたわけです。どうしても病気の発見をしてもらわないと、研究が盛んにならないのではありますまいか。きようは臨床家の方が多いようでありますから、ぜひ組織間およびリンパ管の病気を発見していただきたいと思います。
こういう研究の、全然いままで人が気が付いてないこと、あるいはいままで真理だと考えていることを訂正するような研究はどうしたらできるでしょうか。私がおりましたケンブリッジ生理学教室の創立者フォスター[Michael Foster,1836-1907]は、百年前に初めて英国で生理学というものを始めた人です。この人の書いた14〜16世紀の生理学を主体にした本を見ますと、昔の生理学者というのは皆臨床の医者で、専門家はほとんどいないのです。英国でさえ百年前に初めて生理学の専門家ができたのですから.皆臨床家です。臨床家が生理的な研究をしたものを集めたのですから、これは臨床家の歴史です。
これを見ますと、彼の言っていることは、いま真理だと考えていることは百年先では笑いものになるものもある。そこで現在私たちが真理だと思っているものの多くは間違いりものだというわけになります。一番間違いのないものは何かというと、研究に対する心と研究者の生活態度である。ですから、本当の研究というものは、研究に対する心、言いかえれば philosophy とその人の精進の心が研究を全うするため大切なのだということを、この本は非常によく教えております。
それでは、どうしたらいままでだれも知らないものを見つけることができるのか。あるいは、いままでの間違いを訂正することができるのか。これには、例えばケンブリッジではフオスターは "see and do" ということを言うのです。即ち "Don't think too much” 思ったらすぐやれ。人が何と言おうが、本に何と書いていようが、そんなことはどうでもいい。気が付いたらすぐやれというのです。
これがいかに大事かといいますと、ケンブリッジで私は二年余り、イギリス、イタリア、ドイツ、ソ連、アメリカ、オランダ、方々の人々と一緒に勉強しました。しかし、彼等は俗に言う頭がいいとは思いません。あまり頭がいいといけないので、私がシンシナティで一緒におりましたグスタフ・エクスタイン[Gusutav Eckstein]という野口英世の歴史を書いた人がいましたが、この人は頭が非常にいい。何かやろうと思うと、それはこうなってこうなるというので、やめてしまうのです。ですから、ある意味では鈍でなければいけないようです。あまり頭がいい必要はないのでしょう。
ケンブリッジの生理にはいつも十人ぐらいしかいない、小さな研究室ですが、それがいままでに7人がノーベル賞をもらっているのです。これは "see and do" によるもので、研究費でもなく、研究装置でもないのです。即ち気が付いたらすぐやる、人がどう言っていようが、そんなことは構わない、すぐやる、これなのです。これはいかにこの考えが大事かということをよく証明していると思われるのです。
なぜフォスターがこういう考えを持ったかといいますと、それまでは英国でも内科の医者が生理の講義をしていたのでしたが、それが彼が英国で初めて生理学でフランスのクロード・ベルナールの教室へ一年半留学させられましたからでした。皆さんご存じの『実験医学研究序説』(邦題『実験医学序説』)を書いたこのクロード・ベルナール[Claude Bernard]が、人が何と書いていようが、そんなことはどうでもいい、先入主にとらわれないで、ただ自然の声を聞いて書きつけるだけだ、と言いました。彼はこの心で、いままでハーべーが血管というものは血液の管にすぎないと言いましたが、とんでもない、そこにはコントロールする神経があるということを発見した人です。 [『実験医学研究序説』1865年出版]
何も彼はそのようなものを発見しようと思ったのではないのです。ウサギで脳の実験をしていて、交感神経を出して切りました。そうしたら、幸いにも白いウサギで、耳が目の前にあったわけです。その時耳の色が真っ赤になりました。びっくりしてあっと思ったのでした。これが自然の語るを聞いたことになりました。今度は刺激したら、白くなりました。これが.血管運動神経を発見したゆえんなのです。フォスターはこの研究室に一年半いたのが自分の一生を支配したと言ってます。これは非常に大切がことでから、人が何と言おうが、どうでもいいわけです。ハーベーも、自分は人の本から学んだのではなくて、心臓から学んだということを言っております。
次に、テーマができる、きっかけができる。きっかけができたらどうするかというと、これは実験方法を考えることが大事なのです。人のやった実験方法でやれば、同じことが出るのはあたりまえです。もし間違っていたら、どちらかが間違っただけの話です。ハーベーもそれはちゃんと本に書いております。いままでのような生体解剖をやったのでは五里霧中だ、心臓の収縮は神のみぞ知る、と書いています。そこで考えを変えて、動物とか、そういうようなものの比較生理、比較実験によって初めて迷霧が晴れたと言っています。ですから、皆さんはきっかけを得たら、何か実験方法を考案しなければらないということを教えているわけでありましょう。
ハーべーはまたこう言っております。心ない人と論争するな。学会というものが一番大事なのは、お互いに積み立てのために、協力するための討論をしなければならない。やっつけるための討論をしてはいけない。ですから、あなたはそう言われたが、こうやったらいかがでしょう、ああやったらいかがでしょう、という話が出なければ、学会の意味はない。これはハーベーがよく言っております。
"先物実試"
広島以外からおいでいただいている人もたくさんとのことですが、実はぜひ聞いていただきたいことがあるのです。ご承知とは思いますが、広島市内の銀山町というところで吉益東洞が二百五十年前に生まれたのでした。ご承知のように、吉益東洞は全然西洋医学の影響を受けておりません。その息子が吉益南涯で、その弟子が華岡青洲です。華岡青洲はむろん西洋医学の影響を受けて、ご承知のように世界に先がけて麻酔で手術したわけです。
この吉益東洞が広島におりまして、三十七歳で自分が実験しないものは信じない。本に毒されては病人が治せない。自分は京都に出て、天下の医者を教育する、という考えを持ったわけです。そうしなけれぼ患者が救えないといって、彼は 京都に出ましたが患者が来ないので、飯も食えない。八年間人形作りをして、やっと糊ロをしのいだわけです。
この吉益東洞が広島で考えたことはどういうことかといいますと、先物実試、まず物を先に試せ。これは "see and do" と同じことなのです。彼は張仲景の直系で古医方です。それが、張仲景のキツネにばかされるな、吉益の舌も守るな、こう言ったのです。これはちょうどクロード・ベルナールの言う先入主にとらわれないということです。こうして弟子たちを養成しているのです。
五十年前ですが、私はケンブリッジから "see and do" で鬼の首でもとったように思って帰ってきたわけです。あるとき我々の先輩の富士川游先生の展示会を見まして、この吉益東洞のことを知ってびっくりしたのでした。なにも英国まで行くことはない。 広島の地にこういう人間がいた。言い換えれば、先程お話がありましたが、漢方医学においても、西洋医学においても、同じことなのでしょう。いわゆる研究に対する態度というものは同じことだいうことを、しみじみ感じます。
そして、吉益東洞の息子の南涯が、おやじの「万病一毒」という概念を敷衍しまして、『気血水辨』という本を書きました。この気血水辨というのは何かといいますと、食べ物が肺臓で気になる。体の表面近くは水がある。切れば組織液が出ますから、彼は水と思ったのでしょう。奥のほうには血液がある。気が心臓でこれに乗って全身を循環するというのです。ハーベーとは全然関係なしに考えたのです。そして、これがよどんだり、逆行すると病気になる、こういうことを言ったわけであります。
漢方医学における体液循環、血液循環は中国医学にはありません。これは東洞・南涯が言い出したのでした。こうしたことは 広島が発祥り地で、しかも研究に対するこの態度も 広島が発祥の地でではありますまいか。いままで杉田玄白とか、いろいろな人が漢方医として有名ですが、しかし、こういう人の多くは医学を解説しただけなりです。あるいは輸入しただけなのです。
医学の研究というものを本当に教えたのは、あるいは現在でも吉益東洞以外にはいないのではないかと思うくらいで、私たち広島のものは非常にこれを誇りにしております。こういう素地が広島にはあるわけであります。どうぞこれをひとつ覚えて下さって広島からお帰りくださいますよう、これはの宣伝でございますから悪しからず。先程小川君が盛んに私を宣伝しましたから、私は吉益東洞を宣伝いたします。
釈迦に説法のようなお話しをして申しわけありませんが、これが第一回だというので、研究の心構えについて平素私の思っていることをお話しいたしました。将来この会が大変に盛んになるということをお祈りをしまして、この話を終えます。皆さん、どうもありがとうございました。(文責小川新)
小川新
どうもお忙しいところ、ありがとうございました。我々のために、philosophy、research などいろいろな貴重な話をいただきました。自ら実践してこられた道を淡々と語って、我々を励ましていただいたものと非常にありがたく、感謝しながら聞かせていただきました。
(終わり)
瘀血総合科学研究会の発足を祝して(祝辞)
西丸和義(にしまるやすよし)(日本脈管学会名誉会長)
第一回瘀血総合科学研究会/昭和55年 (1980年)2月22日_広島県医師会館にて
西丸和義:医博,広島大名誉教授,平成2年5月15日卒93才
_______________________________________________________________
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
2007年6月29日 (金) 科学, コラム | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
ある女性行者の乳癌死
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
この女性は嘗て山口県のある病院で乳癌切除手術を受けたが、その五年後に同じ場所に癌が再発した。それから十年ほどして私と出会った。
彼女はこの十年間一切医者に診てもらう事はなかったと言います。
その癌腫瘍は直径が7、8cmの大きなもので、この癌からかなり大量の出血があり貧血の為に顔色も蒼白くなっていた。そこで漢方薬である芎帰膠艾湯のエキス剤を潰瘍の上に振り掛けることにした。
それから二、三年後、島根県温泉津のお寺の行事でお会いした。その時すでに癌が腰や背骨に転移したらしく痛みを訴えられ、その痛みは次第に増しているようだった。
彼女は、「私は、仏の行者としてを生きてきましたが、このような病気になって苦しみながら臨終を迎えるのでは残念でなりません。この病気の終末期にはよろしくお願いします」と真剣に頼まれたのです。
私は、「はい」と言って軽く引き受けたものの、よく考えてみると、そのような事はお寺のお上人に頼まれたほうが良いのにと思いました。しかし私に医師としての鎮痛治療を期待されているのかもしれませんでした。
それから七、八ヵ月たった頃、彼女の家人から電話があり、重篤であるので一度診療に来てくださいと言うのです。私はこの電話の様子から臨終が近いと思い、早速その日の夕方大田市の自宅を訪ねた。みると苦渋に満ちた顔でした。
法華経陀羅尼品には薬王菩薩が法華経説法者を守護すると釈尊や十方の諸仏に約束されています。
この経を読誦すれば何とかなるであろうと思い、私は祈りの中で陀羅尼神呪を誦することにした。
少し病状を聞いてから方便品・壽量品を読誦し薬王菩薩の神呪に入り、「あに、まね、まねい、ままねい、しれい、しやりて、・・・」
と誦しているうちに、薬王菩薩が私の前にお立ちになっていることに気付き、これは薬王菩薩が私をして神呪を誦させておられるのではないかと思いました。
それは経験しかことのない不思議なことでした。きっと薬王菩薩がこの行者を病苦からお救い下さる。それならば、今唱えている神呪は薬王菩薩だけでよいと思い、これを三回繰り返しお題目を十数回ゆっくりと唱えて私の祈りを終えたのです。
その間二十分足らずでした。
このお勤めで彼女の痛みは何とかなるであろう。しかしあまり自信はありませんでした。本人とあまり話すこともなく、この世の最後の別れを告げる気持で帰路についた。
それから二週間ほどして、その後の様子を家人にうかがってみると、あれから三日三晩全く苦痛も無く安らかに熟睡し四目目に目を醍まし、いよいよ臨終も近づいたので、菩提寺である恵珖寺の加藤上人にお願いしてお経を上げていただき、そして静かに寂光浄土に旅立たれたそうです。
by_小川新(1999年)
__________________________________________________________
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
2007年6月24日 (日) 心と体, 信仰, コラム | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
細胞にも“相寄る魂”
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
細胞と気と癌
細胞にも「相寄る魂」
相寄る魂
細胞にも「相寄る魂」があるような気がしてならない。
昭和二十四年、博士課程の研究テーマとして教授から「バセドウ氏病の基礎と臨床」を与えられた。
バセドウ氏病とは眼球が突出し甲状腺が腫れる甲状腺機能亢進症の代表的疾患である。
私は甲状腺組織の増殖は如何にして行われているのかを探求するため、毎晩のごとく顕微鏡で甲状腺の細胞を観察していた。
そこに見える相対する円形ないし楕円形の濾胞細胞が向かい合っている細胞と互いに語り合っているようで、ちょうど結婚という男女の間にも似たようなもの“相寄る魂”だと感じた。
我々の体は数十兆にも及ぶ人体の細胞と数十兆の細菌など他生物体の超有機生物体であり、その一つ一つについてもこの事が言えると思った。これが癌細胞となっても同じように心を持っているのではないか。
これはそれまでの基礎医学にはないものであった。
その頃、基礎医学には多くの仮説があり、この仮説の上にたっている臨床医学の危うさに次第に気づき始めていた。
気と邪気
仏教では人体の生理機能を地、水、火、風、空、という五大素に分けている。
一方我々漢方医は人体の生理を気(き)、血(けつ)、水(すい) の総体と考えている。
この度は「気」について話してみたい。
気というものは病気という言葉があるようにまことに複雑にして奥深い。
気には、貪欲(とんよく)、嗔恚(しんに)、愚痴(ぐち)の三つの煩悩、つまりむさぼること、怒ること、理非のわからぬことという三毒の邪気もあれば、清浄な気もある。
人は様々な汚濁の気、人間以下の阿修羅、畜生、餓鬼、地獄の気の中で生きている。これらの邪気に侵され易く、我々の心の中にもがある。
天を敬い仏を信じ精進すれば、種々の魔性に引きずられて行くこともない。
なによりも、生かされている事を自覚し感謝することが大切です。
“気と癌”
癌細胞とは如何なるものであろうか。遺伝子学によると、何人も細胞に癌遺伝子をもっていることになっているが、それが癌として発病するということは如何なる縁によるものであろうか。
癌と診断されそのことを知らされても、その原因となる「気」というものを自覚することは難しいのです。
それ故、その病になったといえるのです。
例えば、胃癌患者に胃癌のことを話してもなかなか納得しないが、胃潰瘍のことはよく理解できる。他人の背中は見えても自分の背中は見えない。
癌であると知ったとき、自分という個人がそれをどう受け止めるかが大きな問題です。
ある時、三代にわたる癌疾患をもったひとりの青年に言った。
「胃癌になる人は、思いを心の中に貯める人が多い。胃は意(い、こころ)の影響を受けやすくストレスであれば潰瘍となり、物いわぬ意が癌の形となることがある。だから、物を言うことが大切です。
しかし、思うことを全て言いなさいと言っても、考えること、思うことに邪気が多ければ、語れば人を傷つけ自らも傷つくことになる。それならば、あなたは例えばお経を唱え口から声を発すれば、その意は清らかになり、人も自らも清らかになる。胃も清らかになるものです」と。
その後、青年はこれを機に仏教教典を音読するようになった。
このように柔軟な心をもって聞いてくれる人は稀れです。
我々は数十兆の細胞を慈しみ、仏性を供養し荘厳し、泥沼の中に咲く白蓮華のように生きることが大切です。
癌という病気についても心理面から考えることをしなければなりません。
== by小川新 (1999年)==
2007年6月24日 (日) 心と体, コラム | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
古典医学研究の問題点、特に腹証について
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
瘀血研究-第12卷(1993年)
小川新(OGAWA Arata)
古典医学研究の問題点、特に腹証について
序
第1回世界伝統医学技術交流会議を上海中医学院で開催したのは1993年5月2・3日であった。
この場は、各々の教授が診療している4人の中国人患者の協力を得て、日中双方の弁証論治の実際を披露し、中→日、日→中、中→中、日→日という風に互いに検討しあいながら学ぶ臨床的弁証論治の会議であった。その際、伝統医学の方法論は、より高度で、より広いものを求めて、互いに楽しく学習しあうことの大切さを実感したものである。
会議の内容は「漢方の臨床」1993年8号に詳細に報告したが、腹証は、外国に知ってもらうことも必要だが、まず日本に於て、より完全なものを求めて学び合い、教え合うことの大切さを痛感した。
というのは、最近ある研究会で、日本に於て著名な漢方医師の腹証実技の実演を拝見する機会をもったが、私がかねて心配していたように、それは色々と盲点の多いように見受けられた腹証論であり、私も壇上に上がって確認したい熱望にかられたからである。
腹証を研究する場合、腹証と方剤の方意が一致しなければならないと私はかねてから考えてきた。
吉益東洞の薬徴をみても、各生薬の薬徴の中に腹証論がよく出てくるように、私も腹証を通じて薬能論を研究しているが、この困難な問題を少しでも前進発展させるために方剤の方解ないし方剤の方意を一味毎の薬徴で徹底的に追求している。その結果、胸証を研究しなければ腹証も不確実なものとなることを臨床的に確認した次第である。
1.腹証研究の問題点
1-1.虚実弁証への偏向
虚実弁証は、陰・陽、寒・熱、表・裏及び臓腑弁証の中で用いられるものである。
古典医学で、虚実のみを独立して弁証することは、むしろ邪道ではないかと思うものである。
およそ、傷寒論、金匱要略、素問、霊枢などの古典医学では、八綱弁証のすべてを習得する必要がある。望・聞・問・切の四診によって八綱弁証をする必要がある。脈診は勿論あるが、腹証に於ても、この八綱弁証を忘れてはならないことを銘記するべきである。
1-2.胸証及び脊証の無視
腹証だけでは鑑別しにくい場合、胸証・胸脇部の寒熟の虚実を知ることによって、腹証のみでは鑑別しにくい腹証を類証鑑別することが出来る。更に項・脊・腰・臀部を切診する胸腹証で、自信のない証を確実にすることが出来る。
1-3.脈証の精確さ
手の脈状診をはじめ、人迎、趺陽、少陰脈の脈状診が粗略にさいる。
更に手の寸・関・尺における六部定位の脈診が充分に習熟されてないことによって起る八綱弁証の曖昧さが、腹証の見方にまで影響し、腹証の解析に精確さを欠くことになる。脈証と腹証とが不一致の場合、脈・腹のどちらかを捨てねばならない場合とか、主証、客証の判定、新・旧の判定などが出来なくなる。
1-4.傷寒論方剤の処方構成の曖昧さ
古典に記載してある方剤の方意を表現した薬物の並べ方に問題がある。これが腹証研究の障害になっている。
方剤の生薬配列が間違っている場合が多く、薬物の並べ方が混乱していることによって、方意の解説は出来ても、その処方構成による適応証を理解しにくくしていることである。
最近、東京理科大学名誉教授の長澤元夫先生を、広島漢方研究会の特別講演として招待した際の「傷寒論における処方理論について」を聞いて、私のかねての疑問が氷解したような気がしたのである。
すなわち、我々が日常眼にしている「経験漢方処方分量集」や、「康平傷寒論(宋版)」などでは、その処方構成に大きな問題点のあることが分かったのである。換言すれば、「康治本傷寒論」の処方構成、特に小柴胡湯、半夏瀉心湯、甘草瀉心湯、生姜瀉心湯、柴胡桂枝乾姜湯、黄連湯に於ける処方構成は私の腹証の実際と全くと言ってよいほど一致しているように思った。
私は、7・8年前からこれら上記の方剤の処方構成を腹証の現場で解析してきたが、特に、心下痞硬の陰・陽、寒・熱を鑑別しようとする時、康治本が最も納得のいく処方構成になっていたのである。なぜならば私の腹証現場に於て、上記方剤の方意を理解し易いように薬物を並べてみた時、康治本の並べ方と全く一致していたからである。
2.“康治本傷寒論”の処方構成と腹証の問題点
2-1.心下痞硬を伴う小柴胡湯の場合の腹証解析
心下痞硬を伴う小柴胡湯、半夏瀉心湯、黄連湯の鑑別は昔から特に難物とされている。小柴胡湯については、表1のようである。
表1小柴胡湯(処味)生薬配列
・康治本 1.柴胡 2.黄芩 3.半夏 4.生姜 5.人参 6.甘草 7.大棗
・康平本 1.柴胡 2.黄芩 3.人参 4.半夏 5.甘草 6.生姜 7.大棗
・漢方診断の実際
経験漢方処方分量集 1.柴胡 2.半夏 3.生姜 4.黄芩 5.大棗 7.人参 8.甘草
・新編中医学根元要 1.柴胡 2.黄芩 3.半夏 4.生姜 5.人参 6.甘草 7.大棗
私は腹証ビデオ「腹証への誘い」及び「古今腹証新覧」において述べてきたように、小柴胡湯は、まず柴胡・黄芩という生薬複合と、半夏・生姜・人参・甘草・大棗という五味の複合生薬という風に2グループに分けて、この方剤の処方解説をしたものである。
柴胡と黄芩の組み合わせは胸脇部への清熱作用があり、半夏と生姜によって吐気を伴う水滞性脾胃の障害を除くのであるが、人参・甘草・大棗の組み合わせは、胃の気を増進し、和解する働きがあるという風に述べた。腹証の現場で胸脇苦満を説明するには、柴胡・黄芩の組み合わせしかないし、更に心下痞硬を説明するには、半夏・生姜・人参・甘草・大棗の五味の構成しか考えられないので、そのように述べたわけてある。
このように考えて腹証を解析すると、方剤の君・臣・佐使による生薬の並べ方が精確であるのは、康治本の小柴胡湯であったことを確認した次第である。
2-2.半夏瀉心湯の腹証の解析
表2・3・4は、半夏瀉心湯(七味)の生薬配列である。
小柴胡湯では、半夏・人参・生姜・甘草・大棗の五味に柴胡・黄芩が加わっていたが、半夏瀉心湯は、この五味のうちの生姜が乾姜になっている。甘草瀉心湯もそうである。生姜瀉心湯は生姜のみである。
このようにほぼ共通の五味の上に半夏と黄芩・黄連が入ったのが、この方剤の特徴である。半夏の次に黄連が入ることによって、心下から胸中にかけての熱を去り、黄芩は心下に働き胃の実火を瀉すのである。この黄連は黄芩と一緒になって、心下から上の胸部までと心下から下腹に至るまでの熱を瀉することになる。腹証の現場では、胸証に於て心下から下胸部にかけての熱と、心下の中脘部から水分穴、更に下方にむかって、臍部の周辺に至るまでに圧痛のあることが多く、康治本で理解しかほうが、無理なく解析出来るのである。
表2半夏瀉心湯の生薬配列
・康治本 1.半夏 2.黄連 3.黄芩 4.人参 5.乾姜 6.甘草 7.大棗
・康平本 1.半夏 2.黄芩 3.乾姜 4.人参 5.甘草 6.黄連 7.大棗
・経験漢方処方分量集 1.半夏 2.黄芩 3.乾姜 4.人参 5.甘草 6.大棗 7.黄連
表3生姜瀉心湯
・康治本 1.生姜 2.黄連 3.黄芩 4.人参 5.甘草 6.大棗 7.半夏
・康平本 1.生姜 2.甘草 3.人参 4.乾姜 5.黄芩 6.半夏 7.黄連 8.大棗
表4甘草瀉心湯の生薬配列
・康治本 1.甘草 2.黄連 3.黄芩 4.乾姜 5.大棗 6.半夏
・康平本 1.甘草 2.黄芩 3.乾姜 4.半夏 5.大棗 6.黄連
3.瘀血腹証の盲点
3-1.瘀血診断基準について
瘀血の診断基準の大略を決定したらどうかということは、瘀血学会を始めた当初からいつも問題になっていたところであるが、故有地滋教授も公開の場で再々要請されたものである。
これに関する日中双方の診断基準が発表されている。即ち中国の瘀血学会の代表である陳可翼教授(中醫科學院西苑醫院)、翁維良教授(中醫科學院西苑醫院)と全国活血化瘀の中西医結合グループがまとめた中国の血瘀証診断基準や日本における富山医科薬科大学の寺澤捷年教授の瘀血診断基準が発表されている。
これらに対し、私は国際的瘀血診断基準試案を提案した。前記の中国及び日本に於て見逃されている瘀血証に関する診断的欠陥、特に腹証に於ける臨床的情報不足分を補った積りである。長年に亘り、臨床的実験と反省の上に立った腹証の実際から見て、腹証を必須条件として掲げたものである。
この発表に対し、日本や中国に於て、かなり多くの疑問と反対意見が出るであろうことは、当初から予想した如くであった。私としては、この発表を機縁としておこる反対論と疑問に耐えうるものであるかどうかについて、徹底的な反省と解析をしながらこの結論に達したものである。
果たせるかな寺澤捷年先生や陳可翼先生から、このことについての質問が小生に集められた。
その最初は、富山市で富山県援助のもとに催された日中瘀血証シンポジウムの時であった。寺澤捷年氏は「腹証にない瘀血証があるはずではないか」という質問であった。これに対してその場で即答するのが当然であるが、小生としては小生の言う瘀血腹証の全体像を知らないでの質問と思ったので、腹証の技術論のことを考えれば良かったのであるが、公の場でその事を答えれば、日本に於ては個人的名誉を傷つけるように誤解する学者の風土があり、その時には敢えて答えなかった。
医学、特に漢方的治療は、臨床的技術的側面が非常に重要であり、その技術的側面を粗略にして漢方を論ずること、その粗略な漢方的認識を科学化することは非常に危険である。それは我々の科学的認識を前進発展せしめるのではなく、科学という衣を着た虚飾の医学に成り果てるのである。このような似非学者の所謂科学的成果を信じている医師の多いことも事実である。それは、日本東洋医学会という根幹的学術団体に於てさえ、漢方らしい漢方の姿は次第に影を薄くしている。これではせっかく大衆に理解されはじめた漢方も、このようにバブル化しているようでは、西洋医学の本格派からみても、また漢方純粋派からみても、大きな批判を蒙ることとなるであろう。
さて最近の、寺沢捷年教授の講演をみるに、瘀血証という病態像と疾患像を混同しているように見えること、瘀血証の病態像の中で特に自らの腹証における情報不足を反省することなく、多変量解析という数学的手法で飾られているように思われる。腹証を証として論ずる場合、専門家同志の技術交流がなくては、診断基準の基礎づく引こはならない。私の試案は、技術的側面を無視しては日本国内のみならず国際的なものは出来るはずもないし、統一的なものを作ったとしても、架空な部分が混入することとなる事を危惧するものである。
3-2.瘀血腹証の盲点
a)陽明病の心下痞硬で大承気湯、小承気湯など大黄、芒硝を必要とする方剤の心下の腹証は瘀血に入るように思う。特に生肉塊による心下痞硬は勿論のことである。
b)純粋な胸脇苦満は瘀血ではないが、少陽病の胸脇苦満には自覚証があり、その胸脇苦痛を治さないで陳久化すれば、脇下硬として無自覚の脇下の抵抗として、瘀血として遺残することになる。 この瘀血性抵抗はその人のー生にとって重要な病態像の一つであり、癌など色々の難病の素因となっていることが多い。そしてこの脇下硬の病態像は、脇証に於ても長期的な変化として理解し得るものである。
c)下腹部の両側鼠蹊靭帯に治って、そのすぐ頭側に、また両側腸骨前上棘の内側に抵抗と圧痛である。しかしこれらは古くなれば抵抗のみとなる。四物湯ないし地黄・当帰又は龍胆草などの証であるように思うが、更に研究する必要がある。
d)両側腹に強い筋性抵抗がある。これは右側では、当帰四逆湯の腹証と一緒にある場合が多い。 但し、従来示われているような臍傍の左右及び斜右左下、臍下部の抵抗は勿論、瘀血の腹証であることには誤りはないと思っている。
e)恥骨上部や膀胱部には色々な種類の抵抗がある。圧痛もあるが丁寧に診ないと見逃すことが甚だ多い。自覚症が少ないことが多く、見逃されることが多い。また精密検査にも出ないので、漢方家がこれを見逃すようであれば、未病を論ずることは出来ないと思う。しかし骨盤のX線所見では腸仙関節、恥骨、坐骨に骨萎縮や骨硬化像などの変形が既に始まっていることが多い。ここに猪苓湯・四物湯・六味丸・八味丸・桂苓丸・抵当丸の適応症があるようだ。
f)顔や舌のみならず、腰部においても皮膚に色素異常(黒褐色)がある。また、腰臀部の皮膚及び皮下組織に浮腫性抵抗がある。
g)腫瘤以外に頭から以下全身に及ぶ外傷性瘀血があるが、10年ないし40〜50年前の外傷は西洋医学的にも、漢方的瘀血論に於ても、実際臨床の場に於ては見逃されている場合が甚だ多い。このことについては、外傷性潜在瘀血として報告してあるから、その詳細は「漢方の臨床」誌18巻4・5合併号の熟読を要望する。
4.胸証の無視
胸証が殆ど無視されている。ここ2・3年特に強調してきた分野であるが、簡単に要点を述べておきたい。
4-1.胸証の意味について
寒・熱をみることは腹証に於ても大切であるが、胸証に於ては特に大切である。腹証で決定しかねる寒・熱が胸証では簡単に理解できるものである。胸証にも、腹証と同じように陰陽寒熱があることは至極当然のことである。
脈証のみ、舌証のみ、腹証のみで、全身の病態像や病証が理解できて、どんな難病でも簡単に治すことが出来るような名人、達人の先生方には必要のないことであろうが、私のような凡医にとっては、せめてA級の医師になるためには必要なことと思うのである。
4-2.胸証における寒・熱・痰濁について
(1)実火・虚火について
多くは、実火であるが、虚火とみるべきものも少なくない。胸証の方法及び実火、虚火の判定については、「漢方の臨床」40巻3号(1993)で述べたので参照されたい。六味地黄丸を必要とする腹証の場合、知母や麦門冬を必要とする虚火が上胸部から咽頭にかけて存在することが多い。口唇が乾くような乾燥した虚火を感ずるものは、手掌でこれを判断することが出来るのである。
(2)胸熱に対する方剤
1)瀉下剤(寒下):大承気揚・小承気湯・調胃承気湯・備急丸・風引湯
2)清熱瀉火剤:黄連解毒湯・三黄瀉心湯・龍胆瀉肝湯・涼膈散・左金丸・清胃散
3)清熱利湿:茵蔯蒿湯・梔子鼓湯
4)清熱化痰:小陥胸湯・柴胡陥胸湯・竹茹温胆湯・清熱温胆湯・黄連温胆湯・礞石滾痰丸(ぼうせきこんたんがん)
5)辛涼解表:麻杏甘石湯
6)解表攻裏:大柴胡湯
7)気分の清熱:白虎湯・白虎加人参湯・白虎加桂枝湯・竹葉石膏湯
8)和解剤
(a)少陽和解:小柴胡湯
(b)肝脾和解:四逆散・柴胡疎肝散・逍遥散・加味逍遥散
(c)腸胃調和:半夏瀉心湯・黄連湯
9)虚熱
(a)麦門冬湯・味麦益気湯・味麦地黄丸・六味丸・麦門冬飲子
(b)黄連阿膠湯・補陰湯
10)瀉熱破瘀:大黄牡丹皮湯・桃核承気湯・低当丸・下瘀血湯
(3)胸寒に対する方剤(温裏剤)
1)温中理寒:理中丸・人参湯・附子理中丸・桂枝人参湯・大建中湯・小建中傷・当帰建中湯・黄耆建中湯・呉茱萸湯・千金当帰湯・当帰四逆湯・当帰四逆加呉茱萸生姜湯
2)回陽救急:真武湯・茯苓四逆湯・通脈四逆湯
3)温化水湿:桂枝加附子湯・桂枝加朮苓附湯
4)温化寒痰:苓桂朮甘湯・二陳湯・括蔞薤白桂枝湯・括蔞薤白半夏湯・括蔞薤白白酒湯・茯苓杏仁甘草湯・導痰湯
(4)痰濁閉阻の証の生薬にも寒と熱がある。
1)清熱化痰:貝母、括樓仁、天花粉、天竺黄、竹瀝、竹節、昆布、海草、礞石
2)辛涼解表:薄荷、菊花、桑葉、豆鼓、木賊、柴胡、葛根、升麻
3)温化寒痰:半夏、天南星、薤白、施覆花、桔梗
4)辛温解表:麻黄、桔梗、紫蘇葉、荊芥、防風、羗活、細辛、生姜、葱白
5)温裏袪(祛)寒:附子、鳥頭、乾姜、肉桂、呉茱萸、蜀淑、丁香、高良姜、胡淑
5.総括
日本の腹証論は外国に比して非常に発達しているので、出来るだけ完全なものにして、これを海外及び後世に伝えておきたいという願望から、現代の日本の腹証論の問題点を指摘した。
(1)腹証の目的を虚実のみにおくということは誤っていること。
(2)胸証、脊証を無視していること。
(3)脈証をより精確にするよう努力すること。出来れば、人迎、趺陽、少陰脈を脈証のなかに入れること。
(4)処方構成と腹証を研究する場合、まず康治本・傷寒論の生薬の配列を参考にすること。
(5)瘀血腹証研究の種々の盲点について述べた。外国特に中国で、日本のものをまず参考として腹証研究が始まっているが、誤ったり不完全な腹証論を基礎としていることへの危惧の念をこめて、これについて具体的に述べた。
(6)下腹に瘀血があっても、その多くは、下焦のみにとどまらず、中焦、更に上焦へと影響しているので、胸証の必要性を訴え胸証に於ける寒・熱・痰濁を述べた。
(7)昨年春と今年春、「漢方の臨床」誌で胸証を含めた弁証論治の世界を展開してきたが、これをもっと解り易いように「症候による胸腹証の実際」という表題の本を目下整理執筆中であり、その中に腹証瘀血の総まとめを述べる積りである。勿論、技術的側面を徹底的に論述する積りである。
文献
1)小川新:漢方の臨床、40巻、8号、1993.
2)康平傷寒論:日本漢方協会、1983.
3)康治本傷寒論:日本民族医学研究所、1974.
4)長澤元夫:康治本傷寒論講義論 3巻、4巻、長城書店.
5)長澤元夫:康治本傷寒論の研究 頁175-191、健友館.
6)小川新:ビデオ「腹証への誘い」漢方日本図書、1986.
7)小川新:古今腹証新覧 漢方日本図書、1986.
8)陳可翼:瘀血研究、4・5巻、頁106-116.1987.
9)寺澤捷年:瘀血研究、4・5巻、頁109より引用、1987.
10)小川新:瘀血研究、4・5巻、頁106-116.1987.
11)小川新:漢方の臨床、39巻、3号、1992.
小川新 瘀血研究-第12卷(1993年)
=======================
■「康平本/傷寒論」:空海が持ち帰ったと言われ、高野本とも言われる。
■「康治本/傷寒論」:最澄が持ち帰ったと言われ、現存する最古の傷寒論の可能性があり、 延暦寺本・永源寺本・錦小路本などがある。
=======================
■『康治本傷寒論』に関する推薦図書
「傷寒論再発掘」遠田裕政著/東明社
2007年6月20日 (水) 瘀血, 東洋医学, 腹証 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
信仰と癌“牡蛎養殖老人の胃癌”
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
信仰と癌
小川新
法華経には
“三界は安きことなし猶火宅の如し、衆苦充満して甚だ怖畏すべし。常に生老病死の憂患あり。かくの如き等の火、熾然としてやまず、・・・しかもいまこの処は諸々の患雑多し、ただ我一人のみ能く救護をなす”
と説かれている。
病気の中で苦痛を伴う難病の一つに癌がある。何人も苦痛なく安楽に往生することを願っている。そのために我々は日々の信仰に励んでいる。
はたして信仰は我々の願望を充たしてくれるだろうか。この物語はそれを立派に証明してくれました。
“牡蛎養殖老人の胃癌”
この話は、昭和三十年頃の事です。
六十歳を少し越した老人でとにかく徹底した正直一筋の方でした。顔は海で日焼けし、特別な肥料も使わず手間とひまを惜しまず一心に牡蠣を育てるのです。その味は天下の絶品といわれ、小説家の武者小路実篤をはじめ多くの有名人諸家からも賞味せられていたようです。私も二年物の生牡蛎をいただいたことがありますが、口の中で蕩けるように美味しかったのを覚えています。
さて世界大戦後、広島の復興も漸く始まろうとしていたが、廃墟の多い昭和二十三年秋、身延山法主深見日円猊下が老人の菩提寺の慈光寺に巡錫された時、法主様がお歩きになる本堂前庭を新しい真砂を敷き詰めて荘厳するなど一生懸命奉仕されていました。
それから五年ほどして、老人が胃癌で家で寝て居られるということを聞いたので、早速見舞いに行きました。
腹を指して「ここに腫瘤があります」と言われるので、小生も医師として診察してみると大人の拳ぐらいの大きさのものでした。本人はその病気が不治であることをよく知っておられました。
将に末期癌でしたが、不思議なことに全く痛みも無くまた吐くこともなかったのです。「ああ昆布が美味しい、水が実に美味しい」と語るのです。
そして枕元にあった日蓮聖人遺文全集の一冊を私に託し、「君は若いのだから、この御遺文集を読んで信仰に励んで欲しい」と遺言の如く語られました。
この方はそれまで町の老医師に診てもらったことはあるが、あちこちの病院を訪ねることもなく、自らの天命を知って悠然と死を迎え、諦念の中でお題目を唱えながら、「有り難い、有り難い」と言いつつ大往生されました。おそらくお祖師様の居られる霊山浄土にお生まれになられたのでしょう。
この徹底した法華経信者には、医師のホスピスの必要も全く無く、唯、黙然として信心の功徳を信受するのみでした。
然るに最近の日本の現状を顧みると、多くの医師や患者は癌と言う病名が付けられると、恐れる余り最高の医療を求めてあれやこれやと迷うのです。
あらゆる検査や機器を駆使して現在の病症を理解しようとするが、それは病症の一部を示すが癌の底に潜む臓腑関連の病態像を教えてはくれない。
医師として最も大切なことは、患者一人一人に対してそれぞれの癌の病態の流れを冷静に直視し、検査では分からない部分を熟知して治療する事です。
ここに於いては、知識ではなく智慧が大切なのです。知識のみの医学は苦の上に苦を重ねる結果になります。
欲令衆には
“諸仏世尊は衆生をして仏知見を開かしめ 、清浄なることを得せしめんと欲するがゆえに、世に出現したもう・・・”
と説かれているのです。
我々はこのような仏の念に導かれて少しでも仏知見を開き、因果を知るような智慧を頂くことが大切な事です。
それは医師にとっても患者自身にとっても最も大切な心の世界です。智慧のない知識では理想的な癌治療はできません。因果を知らない医師たちが親孝行しようとして一生懸命治療を施し、その結果は親を殺してしまうような悲劇が、医師の家族の中で展開されることは多いのです。
今、我々の身体に数十億個あると言われる体細胞を観るに、その一つ一つが心、仏性を持って生きているのです。一切の病気の中で癌は、言わば提婆達多のような存在です。
法華経によって提婆達多は成仏しました。我々の身体にある癌細胞は、我々が色々と迷ってきた跡の証左とも言うべきものでしょう。我々は、自らは感知し得ない多くの罪障を持っています。ですから、知識を得たとしてもそれが迷惑道の材料にならぬように信仰に励まなければなりません。
信仰によって得られた智慧をもって知識を生かせるようにお題目から智慧と慈悲を頂くよう菩薩道に生きなければならないと思います。
小川新(1999年6月)
2007年6月12日 (火) 心と体, 信仰, コラム | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
なぜ「統合医学」としたのか
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
_________________________________________________
なぜ「統合医学」としたのか
小川新
私が理想的医学として「統合医学論」をはじめて発表したのは1978年でした。
その時なぜ、「総合」でも「融合」「結合」でもなく「統合」としたのか。
■なぜ総合医学としなかったか
さて、統合医学とは何を意味する言葉であろうか。
私が統合医学を総合医学と言わない理由の第一は、
この「総合」を安易に用いる「総合病院」が全国津々浦々にある。
色々な科を備えた総合病院といことですが、各科が単に横ならびに並列したものが多く、私の意図する総合ではい。私はこの総合医学という言葉では、私の理想とする医学の表現に対して非常に誤解を生むであろうと考えたからであります。
結論的に言うと今の所謂「総合医学」は私の意図する総合です。
総合という名称に対するこのような抵抗があったからです。
■なぜ融合医学としなかったか
次に融合という名を付けなかったのは、融合したら新しいものが出来なければならないということになり、漫然と融合という言葉を付ければ、東洋医学や西洋医学の元来持っておる特徴を失う恐れがあり理想とする医学にはならないと考えたからです。
次元の低い東西医学になってくるのではないかと恐れたからであります。
■結合医学としなかったか
次に東西結合医学という表現について申し述べます。
中西合作という名称は中国でよく表現されて使われていますが、これは東西医学に分割した場合、その分割を再び結合して理想的な医学をやろうという意味の名称でありまして、政治的にも東西医学を互いに利用すればもっと良い医学が出来るはずだという政治的配慮によるものが多いと見たからであります。
一般大衆から見れば、そのほうが結合理念の医学は理解しやすく理想的なものであると見えますが、この結合理念にはそれに基づく哲学的理論の背骨が見られない、基礎理論が欠如しておるというところに暖味さがあるからであります。
■なぜ統合を用いたか
そこで最後に統合という名前を用いた理由について箇条書きに述べます。
1.夫々の医学の最高級の技術水準を維持すること
2.病態の流れの中で最高の医療を行うためには、現在その時の病気の流れの最大の証、最も適切な証を時を逃さずにその時を空間的なものとして捕らえる最適の医療を行うことを理想としたからであります。
要するに証の流れの時を空間的に見て最適の医療を行わんとしたときに付けた名称であります。時間を空間に理解しその時その場に応じた最適の治療をすることであります。
3.最高の責任者は、この統合的証に応じた東西医学を自由自在に判断し実践できる能力を持つ人を中心に行うことであり、そうすることによって統合医学的診断と統合医学的治療を実践することが出来るからであります。
そこには理想的医学を実践し得る医療技術者の養成が期待できるのです。
証に応じた東西医学を自由に駆使し得る人材は生まれる。
ここに私の統合医学を世界に発信した目的が存在するのです。
小川新(OGAWA Arata)
______________________________________
[広告]月刊誌「ナショナルジオグラフィック日本語版」
2007年6月 5日 (火) 日記・コラム・つぶやき, 東洋医学 | 固定リンク | コメント (0) | トラックバック (0)
小川古医書館
- 小川古医書館収蔵リスト(excel エクセル版)
- 小川古医書館収蔵リスト(PDF版)
江戸時代~明治の阿蘭陀医学・西洋医学・漢方・本草などの書籍を収蔵
国際社会で自分自身を語れますか? 日本人のあなたに元気と勇気と良識を!
Amazon.co.jp 店外立読みコーナー「産育全書」「産論」
- 『産育全書』復刻版,水原三折《著者の水原三折は探頷器の考案(1835年)、これはウィンケル産科全書に紹介された、また破膜器、カテーテルなどを発明、畳上での出産のために奪珠車を開発などを行った》
- “上臀下首”の発見者・賀川玄悦「産論」
広告
- リンクを取得
- ×
- メール
- 他のアプリ
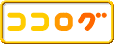

コメント
コメントを投稿