活き活き人担当スタッフ・及川です。先日、地元演劇ユニット「ザ・どらま」の第2回公演を観に行きました。
◎
『釧路と啄木の女たち』(6月30日昼・ジス・イズ2階 ART SPACE)4月の旗揚げ公演ではシェイクスピアが取り上げられましたが、今回は釧路ゆかりの歌人・詩人である石川啄木がテーマ。啄木の妻・節子、釧路の芸妓・小奴、同じく釧路で看護婦を務めていた梅川操という、啄木に関わった3人の女性たちを、異なる3人の女優が一人語るというスタイルです。劇団のように大がかりな人数や舞台セットを必要としない一人語りらしく、小さな空間での公演でした。

←
石川啄木(1886-1912)たまたま、かぶりつきの最前列に座ったんですが、ただ一人狭い舞台に立ち、間近で観客の視線を一身に受ける女優さんたちの緊張感は、きっと大きいだろうなぁなんて思いました。其ノ壱「節子挽歌」(語り手:多胡由紀子)、其ノ弐「小奴慕情」(語り手:林淳子)、其ノ参「梅川ZANGE(ざんげ)」(語り手:辻川睦子)というタイトルがそれぞれ付けられていて、「節子挽歌」では啄木の残した日記や、彼が亡くなった際の葬儀の模様を伝えた当時の新聞記事、啄木亡き後の節子が知人に宛てて自身の困窮を綴った手紙が朗読されました。
続く2つがセリフによる一人芝居の演出だったのに対し、いわばイントロダクションであるこのパートでは、文章が朗読される部分が多く、説明的すぎて単調に感じ、聞いていて少し飽きてしまいました。この日の登場人物3人の中では、節子が観客にとって一番なじみの薄い存在であろうことや、啄木を始めとする石川家の窮状(その家庭には結核の病と貧しさがあふれていました)などを説明するために取られた形だったのでしょうが、例えば啄木の日記の箇所では語り手を更にもう1人立てて朗読するとか、節子の手紙以外の朗読部分を思い切って別にしてしまうといったような、変化を付けるもう一工夫が必要だったのでは?節子の手紙の朗読は感情を込め、訴えるものがあっただけに、そこにドラマの焦点を絞るべきではなかったのかなと思いました。
続く小奴を演じた林淳子さんは、旗揚げ公演のブログでも触れましたが、やはりいいものを持った役者さんだなと思います。文学的才能を信じた愛しい“いーさん”(啄木のことです)への思慕をひたむきに語り、一方で芸妓として売れっ子になる以前、漁師相手に体を売ることを強いられた過酷な過去を明かす、その演技には引き付けられましたね。いじらしい純な思いと、その思いの果てにある凄みを、「女の情念」的なおおげさな芝居に陥ることなく、自然にサラリと演じてみせ、ちょっと他にない存在だよな―と改めて感じました。最後に登場した辻川睦子さんは、今回初めて観た役者さんでしたが、82歳の梅川役を時にチャーミングに、時にシリアスに演じてみせ、こちらも好演でしたね。
舞台の最後、啄木が26歳で死を迎える1年前に作った詩「飛行機」が朗読されたのですが、それを聞いていて、なぜか「なんか中原中也みたいな感じだなぁ」という思いが頭をよぎりました。詩人・中原中也も30歳の若さで夭折しましたが、後で調べたら啄木のほうが先に生まれ、先に亡くなっていたんですよね。彼らが朗読を通してフッと重なり、不思議な気がしました。余談ですが、金と女にルーズだった(失礼!)啄木の私生活のハチャメチャさは、明治という時代に生きた人間のスケールの大きさというよりも、自己中心的なエゴばかりが肥大した現代人(わたしもその一人です)の身勝手さにごく近い気がします。思い切って、この現代に舞台を移し変えた啄木劇が生まれると、案外身近な共感を呼び起こすんじゃないかと思うんですが、どうでしょうか(笑)。ではまた。
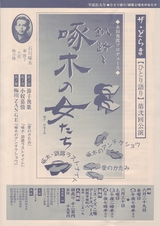
 ミスター及川!分かり易い評論をありがとうございます
ミスター及川!分かり易い評論をありがとうございます
 (笑)
(笑)


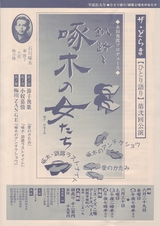



ちなみに小奴はつい4~5年前、啄木の愛人ではなかったという説が打ち出されたんですよね。そうでなかったにしても、啄木は釧路ではやたらもてたようで(笑)