太陽系は約46億年前、銀河系(天の川銀河)の中心から約26,000光年離れた、オリオン腕の中に位置。
- 小
- 中
- 大
江戸幕府5代将軍「徳川綱吉」(とくがわつなよし)は、徳川15代将軍のなかでも「生類憐れみの令」(しょうるいあわれみのれい)を発していることから、特に知名度が高い将軍です。しかし、徳川綱吉の名前に「家」の1文字がありません。それは徳川綱吉が、将軍候補から外れていたことを意味します。 徳川綱吉が、悪法と名高い生類憐れみの令を発した背景には何があったのか。また、将軍候補ではなかった徳川綱吉が、なぜ5代将軍に就任したのか、その理由を掘り下げます。
将軍になる予定のなかった四男

徳川綱吉
「徳川綱吉」(とくがわつなよし)は1646年(正保3年)に、3代将軍「徳川家光」(とくがわいえみつ)の四男として誕生しました。幼名は「徳松」(とくまつ)。
そののち、徳川家光が亡くなり、兄「徳川家綱」(とくがわいえつな)が4代将軍に就任しました。
1653年(承応2年)、元服した徳川綱吉は「従三位左近衛中将右馬頭」(じゅさんみさこんえのちゅうじょううまのかみ)の叙任(じょにん:位を賜り官職に就任すること)を受け、「松平綱吉」(まつだいらつなよし)に改名。1661年(寛文元年)には、25万石の「上野国館林藩」(こうずけのくにたてばやしはん)の藩主となり、参議(さんぎ:官職名)に任命された頃に「徳川」の姓に戻したと言われています。
この頃の徳川綱吉は江戸に住んでおり、館林藩には全く出入りしておらず、徳川綱吉が館林に立ち寄ったのは、生涯でたった一度。1663年(寛文3年)に、兄である徳川家綱に随伴(ずいはん)した初代将軍「徳川家康」(とくがわいえやす)を祀る「日光東照宮」(にっこうとうしょうぐう)へ参拝する「日光詣」(にっこうもうで)の帰り道に、通りかかったときだけと言われています。

徳川綱吉の家系図
儒学への傾倒
徳川綱吉は、父の徳川家光の指示で「儒学」(じゅがく)を学んでいました。例え将軍家であっても兄弟の序列を守り、兄の徳川家綱を尊ぶように躾たかったのです。また、徳川家光自身が弟と家督争いをした苦い経験から、跡継ぎとして早々に徳川家綱を指名。
こうしたことから、弟である徳川綱吉は、兄の補佐役としての活躍を期待されていました。徳川綱吉は、父の期待通り儒学に心酔。これがのちの幕臣にも儒学を奨励したという逸話へと繋がっていきます。
将軍への抜擢
儒学を学んだ徳川綱吉には、将軍職を簒奪(さんだつ:政治の実権を奪い取ること)するような野心はありませんでした。
しかし、4代将軍の徳川家綱は男子に恵まれず、さらに元々病弱だったこともあり、病に倒れて危篤状態に陥ります。徳川綱吉のもうひとりの兄「徳川綱重」(とくがわつなしげ)もすでに亡くなっていたため、徳川綱吉は急きょ徳川家綱の「養嗣子」(ようしし:家督後継者の養子)となり、将軍職を継ぐことになったのです。

徳川光圀
1680年(延宝8年)、将軍職に就いた徳川綱吉ですが、将軍就任前にある問題が起きていたと言われています。
先代の徳川家綱時代の大老「酒井忠清」(さかいただきよ)が、徳川綱吉の将軍就任に反対して、「徳川家」(とくがわけ)と繋がりのある皇室「宮将軍」(みやしょうぐん)を擁立しようとしたのです。
この提案は、「水戸黄門」(みとこうもん)で有名な「徳川光圀」(とくがわみつくに)の反対により却下。徳川光圀は、あくまでも「徳川宗家」(とくがわそうけ)の血筋にこだわったため、徳川綱吉が将軍として抜擢されたのです。
生類憐れみの令とは
5代将軍となった徳川綱吉は、館林藩主の頃から重用してきた「牧野成貞」(まきのなりさだ)を江戸幕府初の側用人として抜擢。そののち、1684年(貞享元年)に大老「堀田正俊」(ほったまさとし)が刺殺されると、後継の大老職を置かず、さらに老中とも距離を取って独断で政治を行なっていくようになります。このなかで発令されたのが、生類憐れみの令です。
生類憐れみの令が誕生した背景
徳川綱吉には「犬公方」(いぬくぼう)というあだ名が付けられていました。「公方」とは、将軍の別称。そのため、生類憐れみの令と言えば「犬を優しく扱うことを命じた法令」というイメージが一般的。生類憐れみの令を発した理由については諸説ありますが、嫡男の徳松が早世したことがきっかけだったという説が有名です。
徳川綱吉は男子に恵まれていませんでした。男子がいないということは、跡継ぎが途絶えること。見かねた母の桂昌院が僧侶に相談します。すると僧侶は「将軍が男子に恵まれないのは、前世の行ないが良くなかったから。子が欲しければ動物を大事にすることです。将軍は戌年なので、特に犬を大事にすると良い」と助言。これを受けた徳川綱吉が、その言葉にしたがって生類憐れみの令を発することにしたのです。
生類憐れみの令が発せられた根底には、徳川綱吉が幼い頃から学んできた儒学の存在もありました。儒学の教えは「人を思いやり、誠実であること」です。徳川綱吉が将軍職に就任していた当時、長い戦乱の名残から暴力で問題を解決する他、放火や辻斬りといった物騒な事件も多発していました。また、重病人を見捨てたり、生まれたばかりの赤子を間引きしたりするなど、世の中は無秩序とも言うべき状態でもあったのです。
このような荒廃した世の中を一新するため、徳川綱吉が思い立ったのが儒学の教えを浸透させること。しかし、そう簡単に人々の価値観や素行は変わりません。そこで、人々に「思いやり、誠実であること」を強制するために導入したのが、生類憐れみの令でした。
生類憐れみの令は135回改定された
徳川綱吉の将軍在位期間は、1680~1709年(延宝8年~宝永6年)の約30年間。その間で生類憐れみの令が発せられていたのは約22年間だとされています。その間、135回もの内容改定が行なわれ、そのたびにお触れ書きが出されました。この回数の多さから、いわゆる生類憐れみの令の正式な開始日については諸説あります。
少なくとも1682年(天和2年)には、犬を虐殺した罪で極刑になったとする記録が存在。また、仁政を敷くために「鷹狩り」(たかがり)も禁じられました。
1684年(貞享元年)には「会津藩」(あいづはん)に対して、鷹の献上を禁止。生類憐れみの令を意識した政策が開始されたのは、この辺りの年代からであったと推測されます。
動物に対する禁制が顕著に提示されるようになるのは、1685年(貞享2年)頃からでした。この年に新たに出されたお触れ書きには、「将軍が御成りになった際にも、犬猫をつないでおかなくても良い」との記述があります。
翌1686年(貞享3年)には、「犬猫を誤って轢かないように気を付け、生類憐れみの志を持つように」とのお触れ書きが出され、ここで初めて生類憐れみという言葉が使われました。

中野御用御屋敷跡
犬の保護は特に手厚く行なわれ、1695年(元禄8年)、大久保や四谷(よつや)、中野に犬を保護する施設(御用屋敷)が作られます。
このとき、保護された犬は約10万頭。翌年には、犬の虐待を密告したら恩賞が出るようにしたのです。発令当初は、この法令を非難したり、わざと違反して犬を痛め付けたりする者もいましたが、そのつど厳格化されていきました。
生類憐れみの令の保護対象
生類憐れみの令が悪法と言われる大きな理由は、対象が犬や猫だけではなかったためです。鳥や魚の殺生禁止に始まり、釣りの禁止や鰻(うなぎ)、どじょうの売買も禁止されていきました。こうなると、当時の人達の食生活にも大きな影響を及ぼすことになります。
こうした状況のなか、禁を破ってでも肉を食べたいという人は少なくありませんでした。実際に、鳥を鉄砲で撃ったことが判明して、11人が切腹した事例もあります。また、病気の馬を遺棄したために、農民の多くが流罪になったと言う事例も。生類憐れみの令に基づいて69件の処罰が行なわれました。
なお、あまり知られていませんが、保護対象の動物に危害を加えた人すべてに対して、処罰が与えられた訳ではありません。荷車を押しているときに寝転がっている犬に気付かず、犬を轢いてしまったなど、やむを得ない事情があれば、罪に問われることはなかったのです。刑罰に処されるのは、保護対象の動物に、わざと危害を加えたとみなされた者のみでした。
江戸の平和維持への貢献
生類憐れみの令を中心とした統治は、徳川綱吉が亡くなるまで続けられます。老中を遠ざけ、側用人を重用していたため、誰も徳川綱吉に意見することもできなかったのです。
徳川綱吉は、息子である6代将軍「徳川家宣」(とくがわいえのぶ)に指示しましたが、徳川家宣は将軍就任後に、順次父が行なっていた規制を撤廃していきます。もっとも、徳川綱吉が望んでいた儒教思想は、ゆっくりとではありますが、少しずつ、確実に江戸庶民の間に根付いていきました。
生類憐れみの令の効果
生類憐れみの令が特に徹底されたのは、将軍のお膝元である江戸でした。地方においては、そこまで徹底することはできず、「尾張藩」(おわりはん)では、禁を破って釣りに76回も通ったという武士もいたと言われています。また、外国との窓口となった長崎県では、オランダ人や中国人も出入りしていることもあって、豚肉や鶏肉を使った料理を食べることができました。
生類憐れみの令は、動物に対しての保護が行き過ぎたため、悪法と見られがちですが、一方で、人々のなかに根付いていた命を軽んじる風習を薄れさせることに成功。諸説ありますが、江戸時代の犯罪件数は、現代の東京における年間の犯罪件数に比べても少なく、特に殺傷事件に関連する件数は、現代を下回ると言われています。
時代背景が異なるため一概には比較できませんが、江戸庶民の間に儒教思想を根付かせる効果はあったとも考えられるのです。
生類憐れみの令は悪法なのか
行き過ぎた動物保護を強要するイメージの強い生類憐れみの令は、後世の創作作品などのなかでも悪法扱いをされます。そのため徳川綱吉は、徳川15代将軍のなかでも特に低い評価を受けてきたのも事実です。しかし、近年ではその評価を見直す流れができています。
前述したように、当時の江戸市中は長い戦乱のため、人々の心は荒廃していました。それを変えるには、強い強制力が必要だったのです。このように思い切った「改革」に必要なのは、それまでのしがらみを断ち切ること。寵臣以外を排除して独裁体制を敷いた徳川綱吉だからこそ実行できたことでした。法令で禁止にしてしまえば、庶民や武家など身分に関係なく、皆平等に処罰を下すことができます。
すなわち、生類憐れみの令は儒学を重んじた結果生まれた、人権を守る法だったという評価もできるのです。
なお、生類憐れみの令は1709年(宝永6年)の徳川綱吉の没後すぐに、一部を残して廃止されました。捨て子の禁止、病人の保護など、直接的に人々の命を守るために制定された法令に関しては、6代将軍徳川家宣以後も継続されています。
徳川綱吉の新しい評価
徳川綱吉は、「忠臣蔵」(ちゅうしんぐら)のなかで「浅野内匠頭」(あさのたくみのかみ)に一方的に切腹を命じ、「赤穂藩」(あこうはん)を改易した将軍として描かれました。
また、時代劇・水戸黄門でも、生類憐れみの令を徳川光圀が軽んじて、徳川綱吉に動物の毛皮を贈るという皮肉に満ちた演出がされています。こういった創作の影響で悪役の印象が強い徳川綱吉ですが、近年では、江戸の秩序維持に貢献した、優れた将軍であったと言う見方が主流となりつつあるのです。
実際に、8代将軍「徳川吉宗」(とくがわよしむね)は「享保の改革」(きょうほうのかいかく)を実行する際に、徳川綱吉の「天和の治」(てんなのち)を参考にしたと言われています。また、生類憐れみの令のなかで、病人の保護や、捨て子の禁止を奨励したことで、道端に死体を放置するなどの非人道的な光景が次第になくなっていきました。
確かに、動物を極端に手厚く保護するという一点に焦点をあてれば、悪法と呼ばれても仕方ない面もあります。しかし同時に発した、人々の秩序を正す法令は、現代まで続く日本の平和を維持する礎になったという見方もできるのです。
徳川綱吉に対する評価は、当時から賛否両論ありました。徳川綱吉に謁見したドイツ人医師「エンゲルベルト・ケンペル」は、自著「日本誌」のなかで、徳川綱吉を「将軍・徳川綱吉は偉大で優れた君主である。儒学を尊び、国と人々を等しく尊重し、彼の下ではすべての人が対等に生活をしている」と評価。徳川綱吉と直接交流したことのあるケンペルのこうした評価は、決して軽視できない意見のひとつと言えるのです。

第5代将軍/徳川綱吉をSNSでシェアする





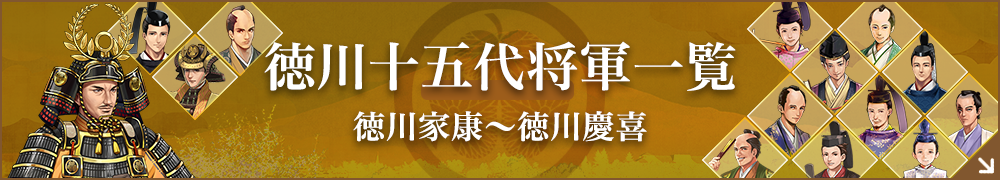




















コメント
コメントを投稿